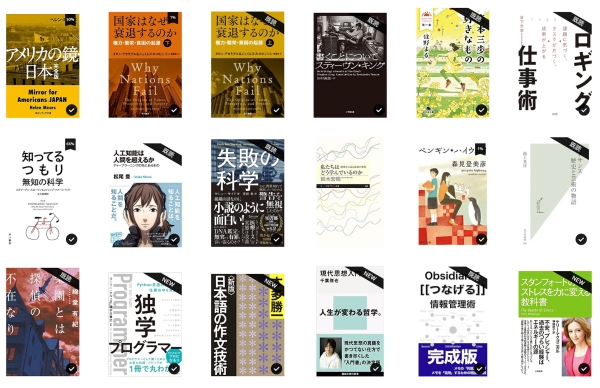僕は紙の本でもKindle本でも、本に書き込んだりハイライトしながら読みます。
でもその細かな方法や意味合いについては色々と変化してきたし、今現在も模索中。
そこで調べてみようと思ったんですよ。「みんなどうハイライトして、どう使ってるの?」って。
でも全然参考になる記事が見当たらない。Kindleのハイライトを例に挙げると、検索上位の記事って大抵
- Kindleには文字をなぞって「ハイライト」する機能があるよ!
- もう一度タップすると削除できるよ!
- 自由にテキストを書き残せる「メモ」機能もあるよ!
- メモとハイライトページにアクセスすれば、一覧で確認できるよ! 便利!
みたいな、薄ーい情報しかありません。Kindle歴10年のユーザーが解説してる記事でもその程度だったので、ウェブ検索にはほとんど期待できないでしょう。
違うのよ。
僕が求めてるのは「Kindle10年使っただけで実績として使えるんだ?へぇー」っていう、「実績」という概念の拡張ではないんですよ。
ハイライトについて、もうちょっと突っ込んだ話が聞きたいんです。
まぁ無いなら書くしかないなということで、今回は僕個人の体験を元に、
- 激烈に「無意味」だったハイライト
- そこからちょっと進めた「簡単な本」用のハイライト
- 「ちょっと濃いめの本」用のハイライト
を紹介しつつ、「それも良いな」と思える記事の誕生を待つという作戦に出ようと思います。
この記事を読まれたあなた自身の考えや方法論、ぜひお聞かせください。
あと一応言っときますが、「俺は15年使ってる」とかいう謎のマウントには誰も興味ないので、できるだけ控えてください。
激烈に無意味だったハイライト
僕は読書家ではありません。軽めのビジネス書でさえ5, 6年前まで全く読まなかったし、それまでは小説をたまに読んでいた程度。
社会人の約半数は本を全く読まないそうですが、完全にそっち側の人間でした。
これはさすがにいかんと思い始め、まず「読書術」から身に付けようと手に取ったのが『レバレッジ・リーディング』。
(別におすすめ本ではありません)
多読よりの読書術本で、ハイライトに関する要点だけを抜き出すとこんな感じ。
- 気になった箇所をメモに書き出す
- メモを持ち歩いて何度も読み返す
紙の本と電子書籍の違いはあると思いますが、要は重要な部分を書き出して、それを何度も読めってことですね。
当時の僕はすごく素直な子で、早速この本の文章をハイライトして読み返してみたんです。当時のハイライト一覧がこちら。
- 読む前に「この本はこれくらいの時間で読み終わるぞ」という制限時間を設ける
- 複数の本を読むからこそ、重要なポイントがわかる
- 一番いいのは、わたしが毎朝決まった時間に風呂に入りながら本を読むように、 すでに生活の一部分となっている習慣と、読書とを組み合わせてしまうこと
- 完璧主義を捨てる
- 必ず読みながら重要なポイントに線を引き、印をつけ、ページの角を折ってください。
昔はこんなふうに、ごく短い「フレーズ単位」でハイライトしていました。で、これを何度も読み返すと。
……3日も続きませんでしたね。ただ読み返すだけなのに。
だって超絶つまらないんだもん。
何もかも失敗だった
これは全然ダメだなと。
別にレバレッジ・リーディングをディスってるわけじゃないですよ?
これは普通に良い本です。たとえば「著者のプロフィールをちゃんと読め!」って教えなんかは、全くその通り。僕はこの本のおかげで、
- MBA
- なんとかアドバイザー
- シリコンバレー
といったキーワードを含むクソ長いプロフィールの著者が書いた本を色んな意味で楽しめるようになりました。すごく感謝しています。

問題はこの本の内容ではなく、ハイライトの方。
ハイライトって付けた瞬間は「お、ここ良いな」とか、「ここはポイントだな」とか思ってるはずなんですよ。ただそれを本から抜き出して一覧にすると、激烈につまらない。
これって何なの?
簡単な本用のハイライト
僕はその原因を「文脈」にあると考えました。
この時期のハイライトは文脈が削ぎ落とされすぎていて、ただのフレーズ集でしかない。だからそれを見返しても心が動かない。心が動かないものは読んでもつまらないし、つまらないことは続くはずもない。
文脈ってのは大事ですよ。たとえばこの本から、印象に残ったフレーズを一か所ハイライトしたとしましょう。
(別におすすめ本ではありません。レバレッジ・リーディングのハイライトがあまりに使えなかっただけです)
「ストレスはないのですか」とよく聞かれますが、とくにありません。 その理由は、メモしているからです。
これだけを後から読み返したとしても、「はぁ?」としか思えません。しかしその後に続く文章を合わせて読むとどうでしょうか。
「ストレスはないのですか」とよく聞かれますが、とくにありません。その理由は、メモしているからです。
頭の中のものは、どんどんメモをして、外部に出力してしまっているのです。 もやもやと考えることもない。
やるべきこともメモにしてありますから、「あれやらなくちゃ」などと考えることもない。頭の中は、常にすっきりした状態にあるのです。これも、メモのおかげです。
このハイライトなら、1年後に読み返したとしても「そういうことね」と納得できます。まぁメモしてもストレスが完全に無くなるとは到底思えませんが。
それはともかく、後から読み返すことを考えるなら、フレーズ単位ではなく前後の文脈まで保存しておく。これが僕のハイライト第二段階です。
ちょっと濃いめの本用のハイライト
ただ文脈を保存するハイライトが通用するのも軽いビジネス書くらいで、何か新しい分野について知る、学びのための本(専門書や参考書、文章量の多いビジネス書など)には使えません。そういう本ってハイライトすべき箇所が多すぎるし、多すぎるハイライトはどうせ後から見直す気にもなれないからです。
だから濃いめの本に関しては「ハイライトを読み返す」こと自体を諦め、単純に「目印」として使うようになりました。その本の文章が
- 主張や問題提起
- 根拠(具体例)
- 結論
で構成されているとするなら、主張の部分にハイライトを付け、「ここからこの話が始まります」という目印にしておくということですね。
目次よりもう一段細かな「小見出し」というニュアンスでしょうか。
つまり、ハイライト自体にはあまり意味が無いという考えが根底にあるということです。
ハイライトを一覧にしたり読み返すより、本の内容をテーマとして「自分自身で考えるきっかけ」にしたり、知識を広げるための「資料として」使う。だからハイライト自体には、目印程度の意味しか持たせない。
というのが現時点での僕の主張ですが、特に濃いめの本に付けるハイライトについてはまだまだ発展途上の段階。あなたの意見や活用法も聞いてみたいところです。
今回のまとめ
- ハイライトを読み返すことを前提とするなら、文脈まで保存しておいた方が良い
- 軽いビジネス書は一応ハイライトしておくと、数年後にどこかで使えるかもしれない
- 濃いめの本にハイライトするのは、おそらくあまり意味が無いと思う
ちょっと面白かった記事
最後に今回のテーマとはちょっとズレるけど、面白味があるなと感じた記事を紹介しておきます。
ハイライトの方法と活用(?)について長々と書かれた記事。
正直、全体的には全然面白くないんですが、この一か所だけには心奪われました。
1冊の本の書き込みを読書ノートに書き出すのは、非常に大きな労力と時間を必要とします。「レバレッジ・リーディング」を書かれた本田直之氏は、彼の秘書に任せているようです。
どうやらハイライトを最も効率的に残し、活用する究極の方法は「秘書に任せる」だそうです。
皆さんも本から学びを得たいと考えるなら、まず秘書を雇うところから始めてください。